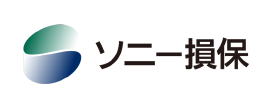Profile
大学では文化情報学を専攻し、数学やプログラミングを活用した絵画の分析などのデータサイエンスを学ぶ。学問と並行して打ち込んでいたのが、小学生から続けてきたバレーボール。キャプテンとしてチームを率い、関西の一部リーグで活躍を続けた。就職活動の軸となったのは、「人と人の間に入ってサポートをすること」。その考えには、バレーボールで担当していたセッターのポジションも影響していると語る。事故の当事者と相手方の間に立つ当社の事業にそうした役割を感じ、そして先輩との距離の近さにも惹かれて入社に至った。

現在の仕事内容
私は現在、マーケティング部門コンテンツ企画部に所属し、主にウェブサイトやスマートフォンアプリの企画・運用を担当しています。私たちの部署が目指しているのは、お客さまがストレスを感じず、なおかつ安心して保険手続きを進められるようなUI/UXの実現です。例えば、サイトを訪問した方が「どこから申込めばいいのか」を直感的に理解できるように、ボタンの配置や大きさ、申込みの導線の仕組み、そして細かな言葉の表現などを、サイトの定量的な分析データも参考にしながら改善していきます。こうしたオンラインプラットフォームだけでなく、パンフレットや満期案内書などの紙媒体の製作も私たちの重要な業務です。また、サイトやアプリは、当社の契約部門など他部門に影響を及ぼすコンテンツでもあります。案件規模によって違いはありますが、多くの部署と連携が必要となるケースもあり、お客さまにとっての使いやすさと、社内・社外での実現可能性をすり合わせていくことに難しさとやりがいを感じています。

これまでに経験した印象的な仕事
最も印象的だった仕事は、火災保険のウェブサイト改善プロジェクトです。この案件は、当時のお客さまから「画面が多くて手続きが煩雑」「同じ質問を繰り返し聞かれる」といった声が寄せられたことをきっかけに始まりました。課題を洗い出す中で、「こう使ってほしい」という当社の想いとお客さまのニーズのズレが見えてきました。当初は、お客さまの手で正確に入力してもらう手続きになっていましたが、実際に使用してもらうと煩雑さや重複感を感じさせてしまっていたのです。そこで、アクセスデータやカスタマーセンターへの問い合わせ、お客さまアンケート、広告部署の市場調査などを集めて、お客さまの理解を徹底的に深め、契約手続きの導線を調整していきました。最終的には、見積開始時点のお客さまの状況に応じて見積りフローを分岐させることでお客さまの異なるニーズに対応し、さらに見積りについても、複数の補償プランを比較できるよう3つのプランを表示させるデザインに改善しました。また、申込ページ数の大幅な削減とともに、申込みに必要な詳細情報の入力には外部サイトを活用して情報を自動で取得し、サイトへ反映する仕組みを構築しました。こうした部門を横断した施策のかいもあり、申込率が前年度より向上するなど、大規模な案件で結果を残せたことは自分にとって大きな糧になったと感じています。
ある1日のスケジュール
-
08:30
出社
スケジュールと
タスクを確認 -
09:00
データチェック
訪問数や遷移率、
アンケートを確認 -
10:00
サイト企画・保全
課題形成、
改善策の企画構想 -
11:30
お昼休憩
自分の仕事のペースに
合わせてランチ -
13:00
社内外ミーティング
部署横断の
チームミーティング -
16:00
サイト企画・保全
改善策の企画構想、
関係部署と連携 -
19:30
退社
業務の振返りと
翌日の準備
私が思う“価値ある「違い」”
“価値ある「違い」”を考えるときに大切なのは、誰を対象にするのかということだと思います。私がこれまで上司から学び、そして経験を重ねる中で自分自身でも実感しているのが、「お客さまのために、自分自身で考え抜くこと」の大切さです。競合他社の優れた企画を参考にすることも勉強にはなりますが、それぞれの企業のお客さまのニーズは異なります。私たちは「ソニー損保に来てくれるお客さま」に向き合って考えなければなりません。当社に対してどのようなニーズがあるのかを追求した上で、「お客さまのニーズを満たすために、自分たちに何ができるのか」をソニー技術を使えるといった当社のメリットをふまえて考えること。そうして生まれてくる提案が、当社独自の“価値ある「違い」”を生み出すことにつながっていくはずです。
私なりの“価値ある「違い」”の作り方
“価値ある「違い」”を生み出すために、まずはお客さまに何を求められているのかをアンケートやウェブサイトのデータを収集・分析することで徹底的に突き詰めていくことを意識しています。こうした姿勢により、企画構想の段階で「お客さまのため」という根本的な軸がぶれてしまうことを防ぐのです。また、新たにサイトやアプリを企画・設計する際は、抜本的なアイデアではなく、まずは今あるサービスを組み合わせることを考えるようにしています。そうしてアイデアをかけ算的に考えていくことは、さまざまな思考の幅を広げ、議論を行き詰まりにくくしてくれます。そして、アイデアを実現する際に大切にしているのが、自分の考えを積極的に発信していくこと。例え、その場では実現しなかったとしても、ある一つアイデアがチームまたは関連部署の間で議論の種となり、当初とは違う形でより優れたサービスになることも少なくありません。このように、「お客さまのため」の姿勢を軸としながら、自らの考えを周囲へ発信し、関係部署とも協力しつつ、アイデアを組合せていくことで、今後も新たな価値を作り出していきたいです。
※掲載内容は取材当時のものです