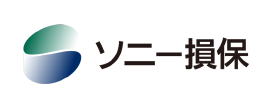Profile
大学では数学を専攻し、大学院まで進学して解析学を研究。数学への興味を深める一方で、カフェやバーでのアルバイトも経験した。数学を活かした仕事をしたいと考えていた矢先に、数学教師や銀行員以外の選択肢として「アクチュアリー」の存在を知り、保険業界に興味を持つように。生命保険会社や信託銀行などを見る中で、既に組織体制や業務システムが出来上がっている大手企業ではなく、比較的新しくかつ今後さらに伸びることが予想されるダイレクト型のビジネスモデルを持つソニー損保に、「ここなら、自分で考えることができる」という期待を持って入社に至った。

現在の仕事内容
現在は、商品部門火新医療商品開発部でアクチュアリー(保険数理士)を目指しながら働いています。私たちの部署は、主に火災保険や医療保険、そしてペット保険のような新規の保険商品を開発しており、その中で私は「成約率分析」という業務を担当しています。具体的には、ウェブ上で契約を進めてくださったお客さまのデータを収集し、どの補償内容が成約につながりやすいかを分析することで、商品開発にフィードバックしていくのです。
入社後は分析業務からスタートしましたが、アクチュアリーの代表的な仕事である「保険料の算定」にも徐々に携わるようになってきました。算定業務における難しさは、火災・風災などの事故率と、月々の保険料のバランスを取ることにあります。「事故率が高い×保険料が低い」という組合せでは、保険会社として成り立たない一方で、「事故率が低い×保険料が高い」の組合せの場合、なかなか成約に結びつきません。こうしたジレンマを抱えながらも、分析を通じて得た新たな観点をもとに、プログラミングを活用して百万件以上のデータを解析し、これまでは気づけなかった数値が見えたときに仕事の面白みを感じます。

これまでに経験した印象的な仕事
印象的だった仕事は、地震に関する保険の商品開発に関わったことです。この案件では、被災時にできる限り迅速に保険金をお支払いするために、日本各地の地震の発生確率を予測し、そのリスクに応じた地域ごとの保険料の算出をサポートしました。まずは地震の発生確率を調べるべく専門機関のデータを活用し、日本全国を細かく分けたメッシュデータを作成し分析を実施。あるエリアでは、X年でYパーセントの確率で地震が発生すると仮定して、一般的な保険契約期間である5年であれば、月々の保険料はいくらになるのかという計算を実際に行っていきました。特に難しかったのは確率の伝え方です。元のデータがどんな事実を物語っているかを私が理解できたとしても、それを数学から実務的な言葉に翻訳しなければ商品開発にはつながりません。できる限り深く理解をし、開発メンバーに噛み砕いて伝えることを心がけ、そうして自分がアウトプットしたことに対して反応が得られたときには大きなやりがいを感じました。
ある1日のスケジュール
-
09:00
出社
タスクやミーティング
など予定を確認 -
10:00
データ作成
契約状況を
損害保険料率算出機構に
連携 -
12:00
お昼休憩
休憩室で昼食or
先輩や同期とランチ -
13:00
部内ミーティング
メンバー全員で
ミーティング - 14:00 分析 成約率分析を実施
-
16:00
照会対応
他部署からの商品に
関する質問に回答 -
19:00
退社
タスクの進捗を
チェックして退社
私が思う“価値ある「違い」”
私が考える“価値ある「違い」”とは、お客さまがどう感じるのかという「知覚品質の違い」を意識することです。保険商品の開発に長く携わっていると、次第に自社の商品と他社の商品の違いを見分けられるようになっていきます。しかし、重要なのは専門家ではないお客さまでも感じ取れる品質=知覚品質です。この点を意識することが、“価値ある「違い」”につながると思うのです。
知覚品質の面白さは、機能だけではなく「お客さまがどんな印象を抱くのか」という側面も品質に含まれることです。その観点から、品質を追求する際には、保険業界での経験の浅いことが強みにもなることもあります。保険業界の目線にとらわれ過ぎず、素の自分の意見も大事にし、「お客さまがどう感じるのか」という視点を商品開発に反映していくことで“価値ある「違い」”につなげていけるのではないでしょうか。
私なりの“価値ある「違い」”の作り方
知覚品質を意識することは、実務における“価値ある「違い」”の作り方にもつながると思います。「保険商品とはこうだ」という共通認識にとらわれ過ぎることなく、素直な意見を述べていくことを大切にしています。
また、こうした姿勢は分析業務においても同様です。例えば、実際にウェブを通じての契約がどのくらいあるかを集計する際の考え方としては、「契約者属性」1人につき1つの契約としていましたが、それでは1人で複数の物件を所持している場合を考慮できていないと気づき、私は保険契約時に受け取る「証券番号」によって集計を行いました。そうした集計方法の採用により、「どんな補償内容を検討した方が、どんな成約率を持っているのか」をより精緻に分析することができるようになったのです。こうした新たな観点を増やしていくことで、ソニー損保を選んでいただきやすくなるような商品を開発することが私の理想です。